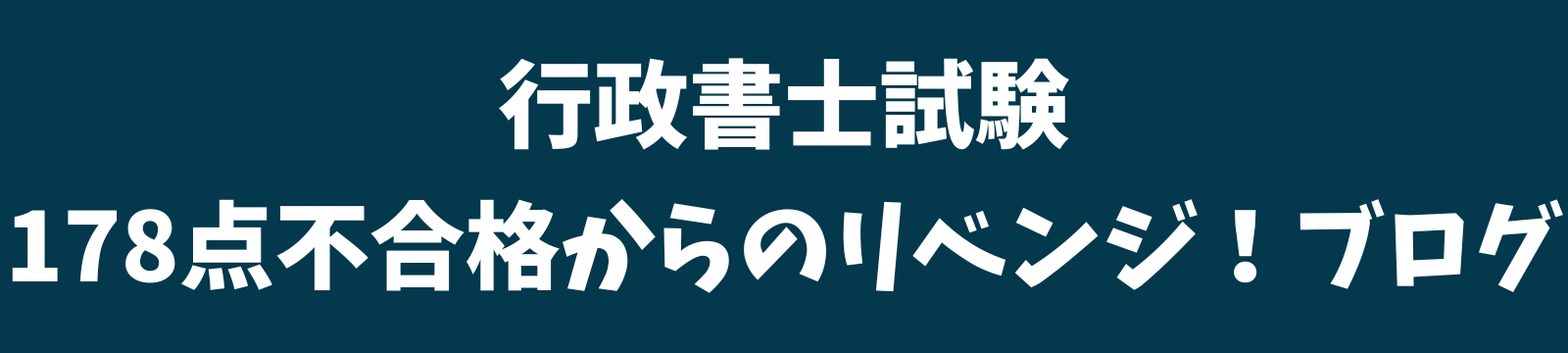今回はざっくりと勉強計画や使用教材などを書いていきます。
2026年(令和8年)司法書士試験対策 学習の基本方針と学習時間
司法書士試験への意気込みと基本方針
まず、今回は必ず受験します笑
そして、この初受験の1回で合格する予定です。今回は受験まで十分な時間があるので、以前のように「何とか勝負にはなるだろう」というレベルを目指すのではなく、10回受けたら9~10回は受かるレベルに仕上げます。
行政書士試験の時と同じく、勉強の基本はテキスト読み込みの大量暗記型でいきます。何度読んでも覚えられないものは暗記まとめ記事で集中して覚える。結局このスタイルが一番安定するはず。過去問などの問題演習はあくまでテキスト暗記の確認作業としてやるだけで、過去問で覚えようとはしません。
もしかしたら行政書士試験よりも司法書士試験の方が安定しやすいんじゃないかと思ったりもしてます。もちろん合格難度と勉強の大変さは桁違いですが。
記述は問題演習をしっかりする予定です。配点が2倍になりましたし。私は以前の形式でも主流の択一逃げ切り狙いではなく記述でまくる戦略を立ててましたが、変更後も同じく記述高得点狙いです。
以前の勉強計画記事:2019年度 司法書士試験 独学合格への学習計画、学習時間、教材(基本テキスト、過去問)選び
司法書士試験 勉強時間について
今回は学習開始から試験まで約55週(13ヶ月)という十分な期間があります。
私がなんとか絞り出して1週間に取れる勉強時間は45時間程度。つまり、試験までに約2475時間勉強することができる計算です。
司法書士試験合格に必要な勉強時間は一般的には3000時間程度と言われています。この数字にはちょっと足りていませんが、そこは行政書士試験+多少の司法書士試験の学習経験でカバー出来るんじゃないかなと思っています。
以前の勉強の貯金はほぼ残っていませんが、マッスルメモリーのように勉強をはじめると少しは戻ってきてくれるのを期待してます。さすがに初学者の状態までは落ちていないはずなので。
司法書士試験 テキスト選び
今までは山本先生のオートマシリーズをメインに色々使っていましたが、今回の受験は思い切ってガラッと教材を変えようと思います。
- オートマがテキスト読み込み型にあまり向いていない(講義型テキストのため、読む分量の割に得られる情報量が少なくタイパが良くない)
- 市販教材だと法改正への対応や誤植をいちいち調べたりするのが面倒
これが理由です。
では今回は何を選ぶ?今はオートマシリーズの他、Vマジック、リアリスティック、合格ゾーン、ブレークスルーなど、独学向け基本テキストの選択肢も増えましたよね。個人的には独学ならやはりオートマが良いのかなと思っていますが。
しかし、自分で色々調べて選ぶのが面倒になったのでもう予備校に任せることにしました笑
さっきも書いたように法改正や誤植も予備校ならすぐ対応してくれるでしょうし、余計な心配をしなくて済みます。
どこの予備校かは受験が終わってから公開する予定ですが、多分このテキスト全部覚えたら受かると思う。読み込み向けでめちゃくちゃ良いです。
記述式だけは市販のオートマシリーズも使います。上でも書いた通り、記述は絶対に得意にして高得点が取りたいのでこの定番問題集だけは外せません。多分ひながら集や論点本もやると思います。
司法書士試験 予備校講座の使い方
というわけで、予備校講座を取ることにしたのですが、あくまで勉強の中心はテキスト読み込みです。完全にテキスト目的で申し込んでます。
基本的に講義動画は倍速でザーッと流し観して終わりの予定です。これで過去の学習の記憶が少しでも掘り起こされるのも期待。ウォーミングアップみたいになると良いなと思っています。
司法書士試験は結局覚えてるかどうかの試験だと思ってるので、講義は導入、オリエンテーションみたいなもんです。本番はテキスト読み込み。ただ、記述式の講義だけは何回も観る予定です。解き方の参考になるので。
答練は時間の使い方の確認と練習の場だと考えます。
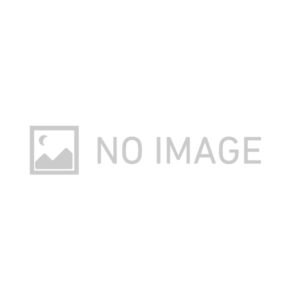
勉強の順番とスケジュール
オーソドックスに民法→不動産登記法→会社法商法→商業登記法の流れでいきます。
内容は予備校講義を上の順番で1回倍速視聴してからテキスト読み込みの暗記作業に入ります。
過去問などの択一問題演習はテキスト読み込みを何周かしてから。記述式の勉強は各登記法の視聴が終わったらスタート。
最後に
今回こそ敵前逃亡せずに完走します!久々の法律学習なので楽しんでます。